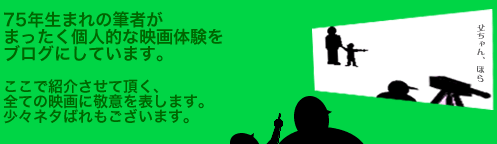07年11月3日土曜日、第8回宝塚映画祭映像コンクールの開催日は文化の日でした。
晴天に恵まれ、きっと各地の文化祭は盛況に進行したことでしょう。
全ての入選作の上映が終了し、審査員の審議も決着がつき、いよいよ表彰式となりました。
入選者がスクリーンの前に並び立ち、各賞の発表です。
実はこの発表までには、いろいろとモタついた進行がありました。
前に並んだはいいがどうやらまだ各賞は決まっていないということになり、今の心境を一人づつコメントし、ひとまず入選の賞状を全員に渡し、いや、その賞状がまだできあがっていない、などなど、司会進行の高橋さんは場をつなぐためにマイクを持ってあれやこれや、ご本人がエキストラ出演した映画の話などをご披露され、大変な活躍でした。
ボランティアを含む少人数の実行委員でこの映像コンクールは運営されており、高橋さんはほとんどお一人で切り盛りしているような按配でした。
大変気さくな方で、この映像コンクールで最も目立って、最も働いて、最も面白い方でした。
映画が好きだという情熱で、こういったイベントを開催されているのだと思います。頭が下がります。
彼は審査員ではありませんが、入選作の選考には加わっておられ、僕の作品は三度ご覧になって入選を決めて下さったとか。
一度見ただけではよく分からなかったのだそうで、
「すいません。ありがとうございます」
と、僕は喫煙所で雑談の際にお詫び申し上げました。
ようやく審査員が会場に戻ってきて、表彰式の始まり。
「宝塚OB会賞」には、松本佳乃監督の「守桜の薫り」が選ばれました。
映像のひらめきをたっぷりと盛り込んだ作品。
風景や小道具を色彩に気を配りながら描写していました。
盲目の女性とチェロを弾く点字補助員との淡い恋模様が、大胆な映像と詩のようなナレーションで綴られます。
映像素材の豊富さに、感心させられました。
「すみれ座賞」には、藤岡佳司監督の「理想の朝」。
ビッグイシューを売るおじさん達を追ったドキュメンタリーです。
(このレポート第一部に感想を書きました)
副賞として広辞苑が渡され、会場から拍手が起こりました。
広辞苑はまだ「拍手」を受けるだけの権威があったんですね。
なんだかうれしかったです。
そしてアニメ部門のグランプリは、東泰子監督の「bar ONE」。
クレイアニメの今や王道とも言えるグロテスクファンタジー(そんなジャンルはありませんが)。
ちょっと不気味なキャラクターたちが出演する小話でした。
キャラクターたちの声が、擬音と言いますか擬声といいますか、適当な音を口で言って字幕で会話を成り立たせるという手法で、この声がなかなか面白かったです。
それと、水彩絵具を溶いたような、おどろおどろしいあの背景は一体どうやっているのか、大変気になりました。
東監督は今回の会場の近くにお住いだそうで、翌日の入賞者の紹介の際にもご一緒させていただいたのですが、どうも聞きそびれてしまいました。
ついに、今回の映像コンクール、グランプリの発表。
審査員長ははっきりと述べました。
「今回はグランプリの該当者はありません」
続けて
「準グランプリが二作品あります」
ということで、僕の作品の「ブルーカラーウーマン」の名前が呼ばれました。
もう一つの準グランプリは、多賀裕見監督の「回り道」という作品でした。
中学生のカップルが翌日の受験を控え、現実逃避の家出をし、電車に乗って海まで行くも結局は帰宅するという物語。
中学生二人の好演が光りました。
なかなかあのような自然な演技を導き出すのは難しいことだと思います。
一緒に会場入りした僕の友人も「あの女の子かわいかったー」と言っていました。
映画で登場人物が魅力的に見えるのは、必ずしも容姿の問題だけでは収まりません。
ストーリーと演出と演技と、いくつもの要素が重なり合って美しかったり可愛かったり、面白かったりするのだと思います。
中学生にとっての重大な事件を、極めて優しい視点で撮りあげた作品でした。
表彰式後には懇親会があり、入選監督と審査員、コンクールの実行委員の方々が同室で乾杯しました。
ここで僕は、審査員の方々から作品について直接、賛否の両論を頂戴しました。
僕の作品を随分と気に入り、強く推してくださったという方と、全くこの映画はダメだということを頑として譲らなかったという方と、ご両人のご意見をたっぷりと拝聴させていただきました。
僕の作品に賞を与えるか否かの議論が、審査を長引かせた原因の一つだったのだそうです。
ご意見をくれたのが白髪の男性で、こういった世代の映画に通じた方々に作品を見てもらえ、また本気で作品についての批評をいただけるのは、貴重な体験であったと思います。
映画を見るとき(演劇でも音楽でもなんでも)、観客は自分の人生と映画経験と、云わばその全ての感覚で作品を受け止めるのだと思います。
誰しも「映画とはこういうものだ」と、知らず知らずの内にある種の基準を持っていて、それから外れるとつまらなくなり、そこへフィットするか、あるいはその想像を超える斬新なものに出会うと面白く感じるものだと思います。
好き嫌いや、観た時の状態(体調や気分や社会的状況など)は、大きく作品評価に関わってきますが、しかし、それでも世の中には傑作と呼ぶにふさわしい多くの者を虜にする映画が確固として存在しています。
懇親会で僕はメッタメタの酷評も受けましたが、しかし彼の仰ることは実によく理解できるのです。
何を言ってやがんでぃ分からず屋め!と粋がってみても、「そう解釈されても致し方ない・・・」「そこは手抜かりがあった・・・」という反省の念は否応なしに襲いかかってきます。力不足なのです。
つまり傑作には程遠い。
褒めて下さった方からは、一生分のお褒めの言葉をいただきました。褒められ過ぎて、こちらが作品の問題点を指摘したくなるほどでした。
自主映画というのは、観るに値しないものだと僕は思っています。
劇場用映画が1800円以内で見れるのなら、何も好んで貧しき自主映画を鑑賞する必然はありません。
残念ながら大抵の自主作品は稚拙でずさんで、つまらないものですし。
そういった現実を踏まえた上で、僕はこれからも自主制作を続けたいと思っています。
なにしろ映画作りは…、楽しいのです。
きっと、面白い自主映画を撮ることは不可能ではないと、どこかで希望を捨てずにいるのです。
表彰式が終わり会場の外に出ると姉が「おめでとう」と言ってくれました。
友人は握手をしてくれました。
賞が獲得できて良かったと、その時思いました。
今回の宝塚映画祭映像コンクールは重要な体験でした。
僕のことを全く知らない方々から準のグランプリという評価をいただけたことは、大変な励みになりました。
より一層の精進を誓って飛行機で帰宅したのでした。

「ブルーカラーウーマン」の1シーンです。