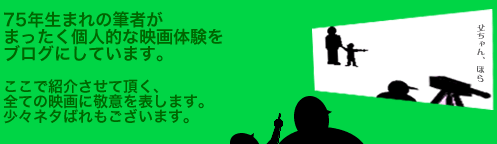【コメントー映画館の白昼夢ー】
1990年。
その日は月曜日だった。
友人二人と、僕は映画館にいた。
前日に体育祭(※)があったため、振り替え休日でその日は平日休校になっていた。
客席には僕たち三人しかいなかった。
やがて上映時間となり館内は暗くなった。
その10日前。
友人が映画を観に行かないかと誘ってきた。
「生協で映画の券が安く買えるんよ。一緒行かん?」
演目はなんだろう。こちらが尋ねる前に友人は言った。
「たけしの映画なんやけど行かん?」
たけし。
当時の僕にとって「たけし」ほど甘美な響きを持つ単語はなかった。
ファンである姉の影響を受け、たけしのテレビは勿論、「ビートたけしのオールナイトニッポン」というラジオ番組も欠かさず聴いていた。
テレビよりラジオの方がたけしを身近に感じることができた。
たけしは度々ラジオを欠勤した。
代わってパーソナリティを勤めるたけし軍団の言によると、現在新作映画の撮影中だという。
撮影現場で誰も台本を持っていない、と弟子のガダルカナル・タカは撮影裏話を続ける。
その場その場で、シーンを作りながら撮影を進めているのだそうだ。
あのたけしが監督をし、しかも今回はたけし軍団が多数出演しているのである。
僕の期待は一通りではなかった。
ところが予告編の始まった映画館には、いくら見回しても我々三人しか客はいなかった。
友人と顔を見合わせてクスクスと笑った。
貸切の状態でいよいよ本編は始まった。
暗闇の中に男の顔がぼんやりと浮かんでいる。
男は用を済ませ、外へ出る。彼はトイレの中にいたのだ。
一転してまぶしい日射しがスクリーン一杯に広がる。
河原の球場で草野球をしているたけし軍団たち。
白い砂埃と晴天。
気だるい休日のお昼どき。
広い空間に打球音が吸い込まれる。
ぽっかりとした日常。
僕は当時野球部だったため、この雰囲気を知っている。
試合の緊張感とは裏腹に、まるでそこに自分が存在しないかのような感覚。
スーッと映画の空気が染み込んできた。
便所から戻ってきた男(柳ユーレイ)に監督(タカ)は言う
「お前よう、野球しにきたのかクソしにきたのか、どっちなんだよ」
「すいません」
この最初の台詞から映画が終わるまで、僕たち三人は終始笑いっぱなしだった。
この映画には、実におかしな出来事がぎっしりと詰まっている。
おかしな出来事がポーカーフェイスでサクサク描かれる。
僕たちにはその一々が面白く、クスクス笑ったり、大声で笑ったり、大変な騒ぎだった。
観客三人という事態も、映画館であんなに笑ったのも初めての体験だった。その後も二度とない。
映画の途中で僕は前の座席の背もたれに両足を放り出した。つられて友人二人も僕に倣った。
誰に叱られるわけでもない。ふと今日が休日だというのを思い出し、うれしくて仕方なかった。
撮影自体が成り行きで進行したように、映画の物語も成り行きで展開する。
野球をし、バイクに乗り、彼女ができ、ヤクザに脅され、沖縄に行き、武器を入手し、最後はドカン。
起承転結のアウトラインは保っているものの、各場面に描かれるのは即興のコントであり、登場人物たちの思いつきの行動である。
自由な気風があった。
映画というものが、こういうことでも成立しうることに驚いた。
このいびつな映画を観たことで、逆に「普通の映画」の存在を認識できた。
テレビでたけしはよく喋る。
だが、映画の登場人物たちの台詞は極端に少なかった。
僕はこの映画でバカみたいに笑ったが、必ずしもお笑い芸人たけしの延長線上に主眼を置いて笑っていたわけではない。
期待していたタレントたけしの映画はそこにはなかったと言っていい。
あくまで映画表現の斬新なアプローチが僕を刺激したのだ。
当初は気づかなかったが、この映画には音楽がない。
音楽がない上に、台詞が少ない。
ということは、スクリーンに映し出される画だけで語っていることになる。
映画が誕生したとき、台詞は存在しなかった。
サイレント映画で十分に観客へ届く表現が可能だったのだ。
もしかすると「3-4×10月」(※)には、現代映画が忘れてしまった映画の本質があるのかもしれない。
説明が増えるほど、映画の映画たる部分は薄れる。
説明なしに観客が自力で「驚き」を発見したとき、映画の感動は作用するのではなかろうか。
そういう意味では、この映画は多くの人にお勧めしたい。
テレビを筆頭に広告や映画でも、説明過剰の向きは当時より拍車がかかっている気がする。
残念ながら公開当時はたけしファンにすら無視されていた作品だが、これは不世出の映画だと思う。
一見の価値はあると思う。
まだ柔らかい頭を持っていた中学生の僕たちは、率直にスクリーンを見上げていたに違いない。
映画文法も映画理論もない。映画とはこうあるべきだという基準も持ち合わせていない。
それこそ成り行きにまかせて、この映画を楽しんだ。
上映が終了し、客席が明るくなった。
僕たちは顔を見合わせてもう一度笑った。
映画館を出たところで、また笑った。
その後、ボーリングに行って、ここでも笑いっぱなし。
翌日学校で、昨日のうちの一人が僕のところへやって来た。
「プログラム見た?」
「いや、まだちゃんと読んどらん」
「たけしの役のことが書いてあったよ」
「なんて?」
「人を殺すと女とやりたくなるホモ。ってよ」
僕たちはまたまた大笑いした。
もしかすると、僕らはただ単に笑い上戸でアホな中学生に過ぎなかったのかもしれない。
※運動会のことを中学では体育祭と呼んでいました。
※「3-4×10月」は「さんたいよんえっくすじゅうがつ」と読みます。3-4×とは野球のスコアボードの表記です。